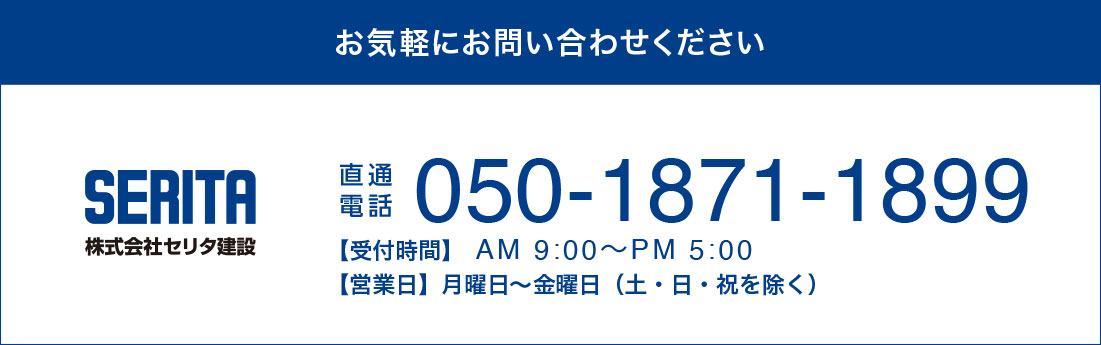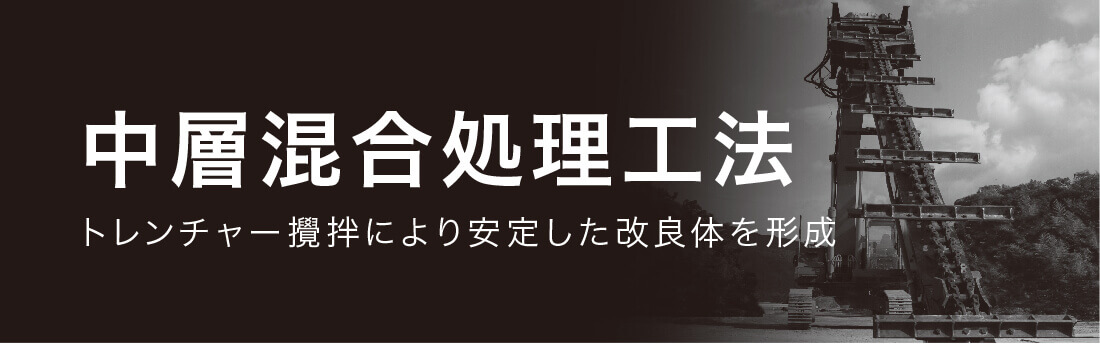施工DXとは?現場が抱える課題と最新デジタル技術を解説
2025年10月15日 建設DX
建設現場では人手不足や作業効率の課題が深刻化し、解決や業務改善を求める声が高まっています。
本記事では、施工DXによるプロセス改革やデジタル技術の導入効果、企業の取り組み事例まで詳しく解説します。
現場運営の効率化や生産性向上に関心のある方に向けて、実践的な情報と具体的なメリットをお届けします。

日本の建設業界におけるDX推進の必要性
施工DX推進は、日本の建設業界全体で避けて通れない重要なテーマとなっています。その背景には慢性的な人材不足や高齢化といった業界固有の課題が根強く存在することに加え、従来からの業界慣習や構造が改革の障壁となっている現状があります。また、資金面での投資余力やデジタル技術を扱える人材の不足も深刻です。特に、これまでアナログで進められてきた現場運営や管理業務は、非効率な作業プロセスや属人的な判断に依存しており、生産性の向上や情報共有の観点でも限界が見え始めています。
さらに、各企業単体での取り組みだけでは効果が限定的であり、業界内の標準化や連携、政府主導の推進政策など全体の取り組みが求められているのが実態です。例えば国土交通省が推進するi-Constructionなどの取り組みは、デジタル化の波を加速させており、補助金制度や人材育成支援も拡充され始めています。
こうした状況を改善するためには、業界固有の課題を一つずつ丁寧に洗い出し、最適なITツールやシステムを導入しながら、行政も含めた全体最適の視点でDXを推進することが不可欠です。DXに取り組むことで、作業効率や業務の品質向上、従業員の負担軽減など多くのメリットが期待できます。
最終的に、建設DX推進は単なる業務改善にとどまらず、長期的な産業競争力の強化にもつながります。今後も業界一丸となった本格的な改革が急務と言えます。
深刻化する人材不足と労働負担
建設業界は現在、人手不足と業務負担の増大という深刻な課題を抱えています。まず、少子高齢化に伴い熟練の人材が減少し、若手の入職者も思うように増えていない現状があります。この労働人口減少が現場の人手不足を招き、結果的に現場担当者一人ひとりの業務負担は増すばかりです。
また、長時間労働が常態化しやすい点も問題です。現場では設計や資材管理、工程調整など多数の業務が立て込んでおり、限られた人員で日々のタスクを回さざるを得ません。さらに、労働生産性の低さも課題として顕著です。ITツールや自動化設備が十分に導入されていないため、手作業による確認や伝達ミスが多発し、無駄な工数が生じています。
それに加え、従来の技能継承が容易ではない点も現場のリスクです。熟練者から若手職人へのノウハウ伝達が属人的になり、高齢者の退職と共に重要なデータや技術が埋もれてしまう事例も少なくありません。このような中、多くの会社や企業がDX推進、業務改善の取り組みを急務としています。デジタル技術の効率的な活用による業務負担の軽減、生産性の向上、技能継承環境の強化が求められる現状です。
現場で浮き彫りになる非効率なプロセスと品質管理の課題
施工現場では、プロセスの非効率化と品質管理の難しさが課題となっています。人手不足により業務全体が属人化しがちで、アナログな手法に頼った管理や作業工程が中心となっているケースも多いです。現場の対応が複雑化する中で、紙ベースの情報管理や個人の経験に依存する判断では、全体の進捗や品質の「見える化」が進まず、組織的な改善も難しくなります。
– 高齢化と2025年問題による人材流出のリスク:高齢従業員が多数を占める建設現場では、今後数年で大量のベテランが離職すると見込まれています。これにより、現場のノウハウや技術継承が困難になり、施工品質の低下につながる恐れがあります。
– 労働時間規制による生産性への影響:2024年以降、時間外労働の上限規制が施行され、工程全体の効率的な運営が必須となりました。これまでよりも短期間で多くの作業を安全かつ高品質に進行させるために、デジタル化や自動化が求められます。
– 現場依存・紙ベース業務の非効率性:作業指示や進捗記録などが手書きベース、電話での逐次対応という現場もまだ多く、これがデータの遅延や情報共有ミスにつながっています。ITシステムやクラウドの導入により、プロジェクト全体の管理や資料共有、課題解決の効率化を図る取り組みが重要です。
品質管理や作業効率の向上には、こうした課題をデジタルで根本的に改革する体制づくりが不可欠です。
デジタル技術で現場を変革する新たな取り組み
施工DXは、デジタル技術の活用によって建設業界の変革を実現する取り組みです。日本国内では様々な産業でDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められており、建設業も例外ではありません。現場の人手不足や複雑な工程、自動化の遅れなどの課題に直面する中、建設DXは業務効率の大幅な向上や生産性アップの鍵とされています。
具体的には、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やAI、IoT、クラウドサービスといった最先端デジタル技術を導入し、現場状況の「見える化」や情報共有の促進、作業プロセスの自動化を実現します。これにより、従来は属人的になりがちだった現場管理も、一元管理や遠隔業務支援が可能となり、作業品質の安定や工程全体の効率化に繋がります。
また、現場ごとの課題や目的、会社の事業規模に応じて適切なITソリューションを選定することがポイントです。システム導入のメリットは、単なる業務負担の削減だけでなく安全性の向上、データを活用した意思決定、生産全体のボトルネック可視化など多岐にわたります。
建設DXを推進するためには、現場の担当者とIT人材が連携し運用体制を整えることが重要であり、国や行政も補助金制度やガイドライン整備を進めて産業全体の変革を支援しています。今後も多様な事例や導入効果が各社から報告されており、DX推進による持続的な成長と業界全体の競争力向上が期待されています。
BIMやAIがもたらす効率化と安全性
BIMやクラウド、AIといったIT技術は、施工DX推進において非常に大きな役割を果たします。各工程やプロジェクトごとに最適な技術を選定し活用することで、現場の業務効率や品質管理を大幅に向上させることが可能となっています。
例えばBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)は、建築物の設計・施工・管理において三次元の情報を一元管理できる仕組みで、設計変更による工程の見直しや現場トラブルの未然防止に役立ちます。加えて、クラウドサービスの利用により、多くの関係者がリアルタイムで情報や資料・データを共有でき、遠隔作業やテレワーク推進も現実のものとなりました。
またAI(人工知能)は作業自動化や現場映像解析、工程管理の効率化などに活用されており、従来人手で行っていた高度な判断業務も迅速かつ正確に処理可能です。IoT(モノのインターネット)では施工機械や各種センサーをネットワークで連携させることで、建設現場の状況をリアルタイムで可視化したり、安全対策や保守の自動化に貢献しています。
このような技術を効果的に組み合わせて運用することで、企業や会社はDX推進による管理体制の強化・業務効率化など多くのメリットを享受できています。
施工管理分野におけるDX推進の背景
施工管理分野におけるデジタルトランスフォーメーションの推進は、今や避けて通れない課題です。建設業界全体で労働人口の減少、高齢化が進行し、特に若年層の人材不足が深刻化しています。建設需要の増加と労働者減少という二重の状況下で、生産性の抜本的な向上が不可欠となっているためです。デジタル技術の導入によって、現場運営や管理業務の効率化が図れ、紙ベースからデータ管理への変革、AIや自動化技術の活用による作業工程の見直しなどが進みます。
2024年からの時間外労働上限規制の施行や、2025年には団塊世代の大量退職といった業界固有の「問題」が続く中、対応策としてDX推進が急がれています。IT・クラウドサービスなどを積極的に導入した企業では、生産工程や品質管理にかかる工数を削減し、限られた人手でも高品質な業務運営が出来る仕組みづくりが進んでいます。
このような変革は、企業ごとの競争力維持、経済全体の成長にも寄与します。今後は関係省庁や業界団体と連携しながら、現場状況に即した柔軟なシステム運営、継続的な技術導入を進めることがより重要です。
施工DX導入による建設現場の変革と効果
施工DX導入は、建設現場に多くのメリットと目に見える効果をもたらしています。現場のリアルタイムな状況や工程進捗を共有できるようになり、多くの担当者や関係者が即座に問題や課題を確認し合い、迅速な対応が実現します。また、安全管理の強化も大きな効果の一つです。センサーやAI映像解析などデジタル技術を導入することで、現場の危険箇所を事前に把握し、事故発生のリスク低減を図れます。
品質管理についても、データ活用による工程の標準化や記録の自動生成により、施工ミスや情報抜けを防ぎ、安定した品質を保てるようになりました。さらに、現場作業者・管理者の業務負担も軽減され、資料作成や報告業務はシステム化、自動化によって大幅な時間削減が可能です。
プロジェクト全体の最適運営がしやすくなり、デジタル技術活用による全体最適化が現場レベルで進行しています。業務効率と生産性が向上することで、企業の競争力や技術力も高まり、持続可能な発展への基盤を築くことができています。
施工DXによる業務効率化
DXを活用することで、施工管理の業務は劇的に効率化され、作業にかかる時間やコストの削減が現場で実現されています。現場運営の課題だった進捗状況の把握や情報共有も、クラウドやITシステムの導入でリアルタイムに確認できるようになり、不明点やトラブルが発生した際にも即時対応が可能になりました。
これに伴って、書類作成や報告業務など手間がかかる作業も自動化され、現場担当者は本来注力すべき工事や工程管理などのコア業務に集中できます。この効率化は、単なる時間短縮だけでなくコスト面の削減効果も合わせて現れ、プロジェクト全体の生産性を大きく向上させています。
また、AIやIoT技術も積極的に活用されており、現場状況の自動記録、資材の管理や安全パトロールの省力化、無駄な工数やミスの減少といったさらなる効果も実現しています。業務効率化と時間・コスト削減は、競争力の維持や事業の持続的な成長に直結します。
遠隔対応とデジタル活用による施工品質・安全性の向上
データの共有や遠隔対応の導入により、施工品質と安全性は大きく向上しています。遠隔臨場をはじめとするデジタル技術の活用によって、現場の状況や工程進捗をリアルタイムで関係部署・担当者と共有可能となりました。これにより移動や現地立会いのための時間を大幅に削減し、効率的な作業計画・工程管理が実現します。
例えばWeb会議システムや現場用カメラの導入で、施工箇所の映像を本社や協力会社にも瞬時に共有しながら、図面や設計データと合わせて複数担当者が同時に確認・相談できるようになりました。
これにより施工現場の進捗確認や作業支援、技術者間でのノウハウ継承、安全パトロール、遠隔点検など多岐にわたる業務が場所を問わず実施できます。デジタル化は無駄な作業の解消やミスの防止にも寄与し、品質・安全両面の大幅な向上に貢献しています。
大手企業によるDX推進の現状
企業による先進的な施工DX推進の取り組みは、建設業界全体の変革を牽引しています。大手企業を中心に、ICT、AI、IoTなどのデジタル技術の導入が積極的に進められ、現場の省力化・無人化、遠隔操作による安全性向上や作業効率化などで具体的な成果が上がっています。
たとえば大成建設ではBIMやIoTで施工モデルの一元管理を実現し、クラウドを活用したリアルタイム情報共有によって施工管理の品質とスピードを両立しています。竹中工務店ではAI画像解析による安全パトロールの自動化や大量データを活用した施工工程の最適化など、業務効率と生産性向上を同時に達成しました。
こうした取り組みでは、データの蓄積・分析・活用を重視した全体最適のプロジェクト管理、現場状況に応じた柔軟なITツール選定が行われています。従来型の現場運営に比べると、ミスや工数の大幅削減、管理品質の均一化、担当者負担の低減といったメリットが明確に現れています。
同時に、複数現場や社内外のパートナーが円滑に情報を共有・連携する仕組みが構築されつつあり、こうした事例は他社や業界全体のDX推進・成功に向けた貴重な指針となっています。今後も次世代技術の導入と運用人材の育成が重要なテーマとなるでしょう。
中小建設会社のDX導入の背景
中小建設会社でも、施工DX導入支援サービスを活用することで大きな成果を挙げている成功例が増えています。導入の第一歩として、複雑な現場工程の見える化や書類・進捗管理のクラウドサービスへの移行が挙げられます。これにより、従来は人手や紙ベースで管理していた資料やデータが、離れた部署や協力会社とも瞬時に共有でき、確認・修正が迅速に実施可能となります。
また、AIを活用した現場カメラによる遠隔状況監視や、IoTによる設備異常の自動通知など、人的リソース不足を補う便利な機能も導入されています。このようなサービスは、中小企業の予算や人員体制にあわせて段階的にDXを進められる点が評価されており、実際に安全性や作業効率、品質管理の向上に繋がっています。
代表的な事例としては、従業員数が限られている小規模会社でも、外部サービスベンダーの導入支援を受けつつBIMモデルやクラウド業務ツールを活用し、課題解決に取り組んだ結果、全体の生産性を向上させたケースが報告されています。こうした支援サービスの利用は中小企業にとって施工DX推進の有効な手法の一つとなっています。
BIM・IoT導入による建設現場のデジタル革新と効率化
BIMやIoTの導入により、プロジェクト管理や現場連携が格段に進化しています。従来インターネットと無縁だった重機やツールもIoT技術によってネットワークに繋がれ、現場状況のデータをリアルタイムで収集・活用する環境が整いました。
2020年の5Gサービス開始を契機に、建設現場での大容量通信・低遅延通信が可能となり、次世代型建機の実用化が急速に進展しています。MC(Machine Control)やMG(Machine Guidance)など、自動化や精度向上を実現した建設機械の導入によって、職人の経験や勘に頼る部分が減り、省力化・省人化につながっています。
具体例としては、GNSS(全球測位衛星システム)による高精度な位置情報取得を活用し、丁張りや測量の工程を省略しつつ、効率的で安全な施工運営が可能となっています。
こうした最新事例は、プロジェクト全体の工程改革やデータ駆動型の意思決定を促進し、建設業界の競争力強化と品質・作業効率の向上に大きく貢献しています。
施工DX推進における課題と全体最適アプローチ
施工DX推進にあたっては、業界の構造・慣習、資金、そして人材の問題が依然として大きな課題となっています。建設業界は長年アナログな運営が根付いており、デジタル技術やITシステムの導入を阻む壁となっています。加えて、中小企業ではDX導入に必要な初期投資や継続的維持費の負担、人材不足やノウハウの継承難といった悩みも深刻です。
現状を変革するためには、社内だけではなく業界全体での取り組みが不可欠です。業界全体のガイドラインや情報共有の仕組みづくり、IT人材の育成強化、行政や関係機関による支援策など複数のアプローチが求められます。また、現場環境の改革と同時に働き方改革の加速、時間外労働の削減につながる企業風土の見直しもポイントとなります。
単にツールを導入するだけでなく、目的に応じたデジタル技術の活用・定着、全体最適のプロセス構築まで一体的に推進することで、本質的な変革と課題の解決が進み、建設業の成長と持続可能性に大きく寄与します。
施工現場におけるデジタル技術による技能継承と人材育成
デジタル技術の継承・育成は人手不足解消の有効な取り組みの一つです。従来、職人の暗黙知とされていた技術・技能を、AIや映像解析などデジタルツールで可視化・解析し、そのデータを資料や動画コンテンツとしてまとめることで、若手への技能継承が効率的に進められるようになりました。
例えば、熟練工の作業を映像で記録し、重要な工程やコツをテキスト・数値モデル化して研修プログラムに活用することが一般的になってきています。また、スマートフォンやクラウドを使った遠隔指導、技術研修動画の共有など、場所や時間の制約を受けずに教育が可能になりました。
このような取り組みは、成長産業への変革を目指す中で重要な役割を担い、人手不足・技術伝承の双方の課題解消に大きく貢献しています。会社全体で取り組むデジタル活用や、自社モデルの研修体制づくりが、技能者育成の効率化と品質向上につながります。
施工DX推進による持続的成長への挑戦
建設業界は大きな節目を迎えています。2030年には最大94万人の技能者が不足すると予想されており、業界全体が危機感を募らせています。国土交通省によるi-Construction政策や補助金制度など、施工DX導入を促進する環境が近年急速に整ってきていることで、現場改革や業務改善に本格的に取り組む会社や企業も増えています。
このチャンスを活かすには、最新のデジタル技術や運用事例を積極的に学び、コンサルタントや外部サービスとの連携、国や行政による支援制度の活用が欠かせません。各社独自の取り組みに加え、産業全体で協力し合い持続可能な成長を目指すことが求められています。
施工DX推進はプロジェクト管理、品質・安全強化、技能継承、業務効率化、全体最適化まで多様な分野に波及効果をもたらしています。今後の可能性を最大化するためにも、まずは展示会や勉強会への参加から、実践的な情報やサービスに触れ、次なる行動に踏み出すことをおすすめします。
参考文献
https://www.issoh.co.jp/column/details/7851/
https://www.kentem.jp/blog/construction-dx-assignment/
https://exawizards.com/column/article/dx/dx-construction/