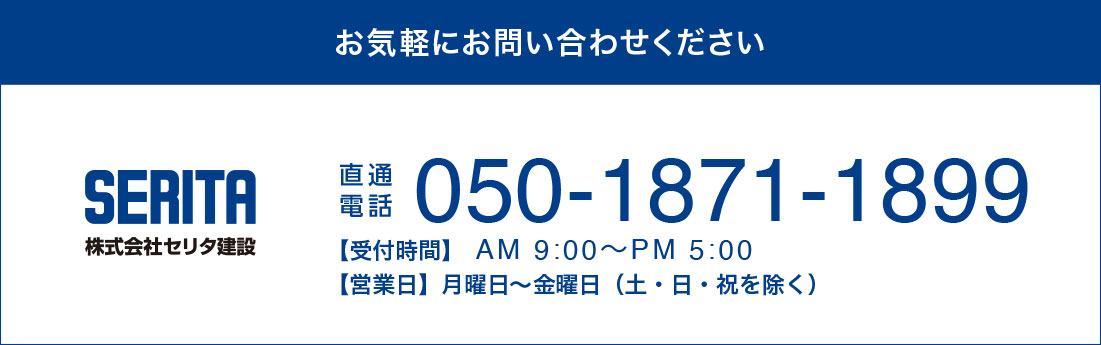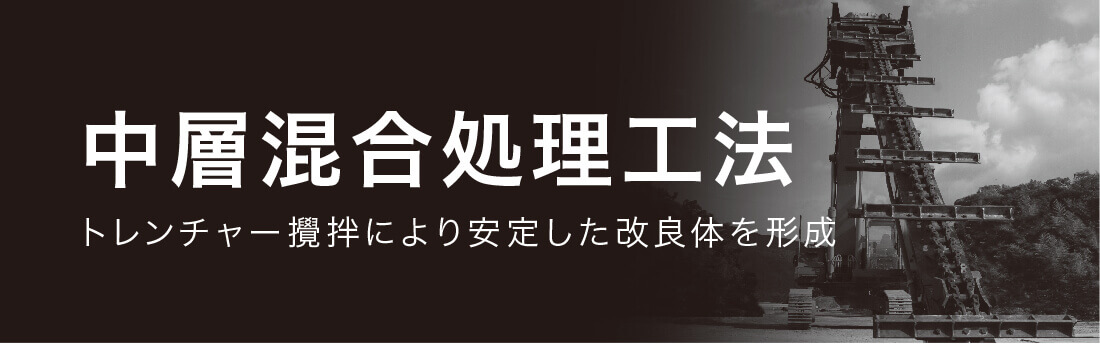低炭素建設の最新動向とCO₂削減事例を徹底解説
2025年10月30日 環境
近年、CO₂排出削減が求められ、建設や開発分野でも低炭素技術の導入が進んでいます。
建物や土木工事など各工程で取り組みが強化され、省エネや再生エネルギーの利用、カーボンニュートラルの推進が重要な社会課題となりました。
この記事では、最新の低炭素建設トレンドや国内外事例、導入方法、普及の動きまで具体的に紹介します。
先進的な技術や事業の効果、今後の発展可能性についても、関心に応える内容を提供します。

低炭素建設が業界に求められる理由と背景を徹底解説
建設業界では地球温暖化対策としてCO₂排出削減の重要性が増しています。国土交通省の資料によれば、日本国内のエネルギー消費量のうちおよそ3割が建築物に起因しており、そのため、建築・土木分野でのカーボンニュートラルの実現が喫緊の社会課題となっています。脱炭素への転換は単なる企業経営の話題にとどまらず、環境負荷や資源消費の低減、持続可能な開発の観点からも不可欠です。再生可能エネルギーや低炭素資材の導入、省エネ性能の強化に取り組む企業が国内外で増加し、業界全体で技術革新が加速しています。たとえば、従来よりもCO₂排出を抑えるセメントや、現場での省エネ施工技術の導入、排出量の徹底的な算定および管理方法の見直しが進んでおり、その効果として環境負荷の削減はもちろん、社会的評価や事業価値の向上にもつながっています。企業によるこうした取り組みは全体の温室効果ガス排出量に大きな影響を与えるため、今後も新たな技術や運用方法の普及・推進が業界発展の鍵になるでしょう。低炭素建設への動きは、社会全体にとっても持続可能性を備えた未来の実現に向けて重要な一歩を提供しています。
CO₂排出量削減がもたらす環境・社会への持続的な効果
CO₂排出量の削減によって、環境への負荷が確実に軽減され、地球温暖化の進行を抑えることができます。地球温暖化は世界規模で深刻な課題となっており、その要因であるCO₂排出の抑制は、産業界・建設分野ともに不可欠な取り組みとなっています。低炭素コンクリートの使用拡大は、CO₂排出削減を推進する最新の技術の一つです。こうした低炭素資材の普及や導入が進んだ場合、企業は気候変動対策やエネルギー管理、資源循環の面でも先進的な姿勢を示すことになり、社会から高い評価を受ける機会が増えつつあります。近年は、環境負荷低減への積極的な対応ができていない企業自体が「責任ある社会企業」として認識されにくくなる傾向もありますが、対策に積極的な企業は評価が向上し、新たなビジネス機会や資金調達面でのメリットも生まれています。低炭素コンクリートを始めとした新技術の導入は、建設業のみならず社会全体の持続可能性や地球環境の維持・改善にも大きく寄与していくと考えられます。今後もCO₂削減のための具体的な活動や方法の普及が、経済・社会全体への良い効果をもたらすと期待されています。
低炭素建設技術の最新動向と国内外の開発ニュース
建設資材分野では、CO₂排出削減に資するさまざまな技術開発が進展しています。例えば、低炭素セメントは、原料の石灰石使用を抑えて代替材料を積極的に活用することで、CO₂排出を大幅に低減する成果を上げています。また、炭素固定型コンクリートは、その製造段階でCO₂を吸収し、材料自体に炭素を固定する革新的な技術として注目を集めています。さらに、グリーンスチールでは水素利用が拡大され、発電やコンクリート、生産工程全体の排出低減に貢献しています。木造建築の推進も見逃せません。木材は二酸化炭素を固定する建材であり、特にCLT(クロス・ラミネーテッド・ティンバー)技術の発展により、大規模建築物にも活用できるようになり、持続可能性向上へ繋がっています。産業界のみならず、社会全体の低炭素化目標・技術革新のベースとして、今後もこうした技術の普及・導入が日本国内および世界規模で加速していくと考えられます。この動向は建設分野の環境対応と事業競争力において重要な位置を占めています。
建設現場でのCO₂算定と排出管理方法の基準やポイント
建設現場でCO₂排出量を適切に算定し管理するためには、電気、軽油、灯油、水道などの消費エネルギーだけでなく、主要資材ごとの製造時排出量まで含めたきめ細やかな管理が求められます。従来多く用いられてきた一律係数による排出量算定方法では、実際の削減効果が反映されにくく、例えば排出量の少ない高価な資材が過大評価されることもありました。そこで近年は、個々の資材や工程ごとの理論排出量を実測値やライフサイクル評価などで詳細に把握し、CO₂の削減努力が建設物全体の排出量にきちんと反映される新しい算定・管理アプローチが広まっています。工事契約においても、カーボンニュートラルへの取り組み状況自体を評価する試行工事が導入され、排出量の少ない建設機械・資材の使用や、現場のエネルギー使用管理の「見える化」が進展しています。国際的にも、SteelZeroやCoなど脱炭素資材普及を目指す取り組みが始まっており、日本国内でも今後さらに高精度な排出量算定基準の導入や、工事ごとの詳細な成果管理が標準化されていくでしょう。こうした動きは現場管理体制や全体の環境負荷削減に効果的です。
低炭素コンクリートやセメントの製造・使用事例を詳しく紹介
建設業界では、温暖化対策としてCO₂排出削減と環境負荷軽減の取り組みが本格化しています。なかでも国内外で関心を集めているのが、従来のセメントに比べ大幅なCO₂削減が可能となるジオポリマーなどの低炭素コンクリートの導入です。この低炭素コンクリートでは、廃棄副産物や産業副産物を原料とし、セメント使用量を抑えることで、建設工程全体のCO₂削減を実現しています。実際の導入事例では、オフィスビルや公共施設、橋梁、トンネル工事などで従来コンクリートの代替として活用され、その高い性能と耐久性、省エネルギー効果が実証されています。さらに、コストや工事期間、性能評価、安全性などを総合的に検討したうえで導入を進める企業も増えています。建設分野でのこうした低炭素材料の普及は資源循環・サステナビリティ実現の観点からも重要な社会的意義を持つため、今後も脱炭素・省エネルギー志向と連動してさらなる技術開発と拡大が期待されています。導入を検討する場合は、施工事例や費用対効果など、最新のニュースや資料を参照頂くとより具体的なイメージが得られます。
原料・資材調達から工事・施工までのCO₂削減対策の取り組み
世界的な脱炭素・カーボンニュートラル推進の流れを背景に、日本でもパリ協定の目標達成に向けて、温室効果ガスの排出削減が求められています。特に、建設分野では原料や資材調達段階から工事・施工の各プロセスでCO₂排出低減への対応が重要です。法制度面では2021年4月に建築物省エネ法が改正され、省エネ基準の対象が中規模建築物へ拡大されました。省エネ基準や再生エネルギー導入の推進は、省エネ性能に優れた建築物の設計・評価を促進し、これまで以上にCO₂削減効果を発揮することが期待されています。また、材料や建設方法の工夫、再生可能エネルギーの活用など、産業界・企業ごとの取り組みが進められています。今後も、2050年カーボンニュートラル達成や2030年の中間目標に向けて、多様な技術導入・制度面の強化が求められ、全体として環境負荷の大幅低減が実現可能と考えられます。
再生エネルギー利用・燃料転換による建設現場のカーボンニュートラル促進
建設現場でのCO₂削減に向けては、電動や水素燃料を活用した建設機械の導入が進行しています。従来型のディーゼルエンジンでは大量のCO₂が排出されていましたが、電動建機への切り替えや水素エネルギーの積極利用によって、施工現場における排出を抑えることができるようになりました。さらに、発電や重機の運用用電力に太陽光発電やバイオマス発電など再生可能エネルギーを組み合わせることで、より一層の省エネ・低炭素化が実現されています。これに加え、AIやIoTといった先進技術を施工プロセスに取り入れ、生産性向上やエネルギー消費の最適化を図る事例も増加しています。今後も、現場ごとのエネルギー源や設備、運用方法の見直しが、建設業界全体のカーボンニュートラル達成を強力に推進していくと考えられます。
建物・土木分野で実践される省エネ設計と性能評価の新基準
建設分野では省エネ設計と性能評価を重視する「建築物省エネ法」が制定されており、エネルギー消費性能の向上を目的に数値目標や基準が設けられています。最近の法改正や基準の見直しでは、エネルギー消費量の約3割を占める土木・建築領域での省エネ性能向上が一層強化されている点に注目が集まります。また、木材利用の規制緩和によって、建築分野での木材需要が高まり、再生可能で炭素固定効果も高い木材の用途拡大が促進されています。加えて、国土交通省では「低炭素型建設機械認定制度」を創設し、省エネ化機械の普及推進にも積極的に取り組んでいます。これらにより、建設業全体でCO₂削減が期待でき、社会的評価や産業競争力の向上にも寄与しています。今後も、性能評価基準の精緻化とともに、エネルギー利用の高効率化や低炭素な建設工程の普及が重要な課題となるでしょう。
段階的導入と業界全体への低炭素技術普及の推進事業
建設機械からのCO₂排出増加が大きな課題となるなか、リチウムイオンバッテリー搭載や電動油圧ショベル、水素エンジンなど化石燃料に依存しない新型建設機械の導入が始まっています。こういった低炭素型機械の普及に合わせて、国土交通省による認定制度の検討、融資支援等も行われています。認定を受けた建設機械を取得する場合、国の制度を活用した資金調達も可能になるため、導入促進の効果が期待されています。さらに水素エンジンは発電利用にも広がっており、産業の脱炭素化に資する新たな方法として注目の動きです。今後は、社会全体・産業構造の変化に合わせて低炭素技術の段階的導入と普及が進み、脱炭素目標の達成や新たな事業価値の実現につながります。
CO₂排出量低減に貢献する建設機械・設備の運用改善事例
建設業でのCO₂排出増加の主な要因である建設機械の運用について、脱炭素化に向けた具体的な改善事例が増えています。リチウムイオンバッテリー搭載機や、電動油圧ショベル、掘削機といった非化石燃料機械の投入が進み、現場でのCO₂排出量を大幅に低減しています。また、ディーゼルエンジンからの転換だけでなく、水素エンジンを搭載した建設機械の開発・導入も新たな動きとして現れています。これらの低炭素型建設機械は、運用の省エネ効率や燃費性能を向上し、工事全体でのCO₂削減と生産性アップが可能です。認定機械導入には国の融資制度が利用できる場合もあり、今後は企業全体の工事計画や現場管理において、こうした機械・設備の導入がますます重要性を増していくでしょう。加えて、水素は発電や他分野でも活用が進み、今後さまざまな工事プロセスへの応用拡大が期待されます。
国内企業が進める低炭素建設プロジェクトの先進事例集
国内の建設関連企業は、脱炭素に向けたさまざまなプロジェクトに積極的に取り組んでいます。代表的な事例として、鹿島建設株式会社、清水建設株式会社、戸田建設株式会社などが自社の脱炭素推進計画や技術導入・普及に取り組み、業界全体のCO₂排出量削減に貢献しています。例えば、現場での低炭素コンクリートや再生資材活用、省エネルギー施工手法の導入、新たな製造技術の開発・評価、エネルギー由来のCO₂算定方法の徹底など、最新技術や運用改善策を駆使して成果を上げています。企業ごとの活動は産業界を牽引する重要なアクションであり、今後も社会全体への低炭素技術普及や省エネ基準支援、政策対応の進展が求められています。これらの先進事例は業界や他企業への良い刺激となり、真にサステナブルな社会の構築につながっています。
コスト面や採算性を含めた低炭素建設の課題とその対応策
低炭素建設が進む中で、コスト面や採算性の確保が課題として挙げられています。建築分野のエネルギー消費が全体の約3割という現状から、省エネルギー性能の高い資材や先進技術の導入は避けて通れませんが、従来工法に比べて建設コストが上昇するケースもあります。この課題への対応として、国や自治体の補助金活用、長期的な運用コストを含むライフサイクルコストによる評価、サプライチェーン管理や資材調達方法の見直し、設計・施工プロセスの最適化などが求められています。低炭素技術や再生エネルギー設備の導入は、初期投資こそ必要ですが、将来的なエネルギー消費やCO₂排出削減、企業ブランド価値の向上、社会的評価や市場競争力の獲得など多くの効果をもたらします。実際に企業の取り組み事例では、費用対効果を総合的に評価しながら脱炭素化を推進し、最終的には全体コストの最適化や新たな事業機会の創出につなげる動きも目立っています。採算性と社会的義務のバランスを取りつつ、持続可能な建設プロセスへの転換が重要なテーマです。
政策支援と社会的評価が低炭素建設普及を強化する理由
建設業界が脱炭素化を推進する最大の意義は、ビジネスモデルの変革や産業競争力強化にあります。政府による気候変動対策の強化、2050年までのカーボンニュートラル達成目標の掲示を背景として、政策支援の下で技術革新や低炭素技術の導入が促進されています。さらに、エネルギー削減を統合した新たな建設事業は、持続的な成長性やブランドイメージ向上、資金調達面での有利性を企業にもたらします。RE100など社会的なサステナビリティ活動への参加や、環境配慮に積極的な姿勢の示し方次第で、入居企業や取引先との関係強化、採用応募数増加など実務的な効果も期待されています。投資家や金融機関からも、将来の建設プロジェクト評価や融資条件として脱炭素への取り組みが問われる傾向が強まりつつあります。政策支援と社会的評価の両面で、脱炭素・低炭素建設の導入は今後の業界動向や企業存続の条件としてますます重要性を増しています。
今後の目標と世界で期待される低炭素建設の発展可能性
建設業界の脱炭素化推進においては、CO₂排出量把握、低炭素建設機械の導入、低炭素素材や工法の工夫といった多様な取り組みが進められています。現場での施工マネジメントだけに留まらず、原料選定から設計、運用まで全ての段階で炭素削減を意識した戦略が求められています。日本国内はもちろん、グローバル規模でもCO₂削減とカーボンニュートラルへの期待や目標が高まりつつあります。企業や現場単位で自社のCO₂排出源を見直し、導入可能な技術や手法を使った実証を重ね、業界全体に知見を還元していくことが今後の発展を支える鍵になります。省エネ化や低炭素技術の普及による建設産業のイノベーションは、地球環境と社会への持続的な価値提供につながると考えられます。
低炭素建設の未来と社会への価値―まとめと今後の展望
低炭素建設は、環境負荷低減やカーボンニュートラル社会の実現に大きく貢献し、社会や産業全体のサステナビリティ向上に寄与します。技術革新や再生エネルギー導入、エネルギー管理方法の進化などにより、建設プロセス全体でCO₂排出の抑制が進み、今後の業界標準として確立されていく可能性があります。こうした取り組みはより多くの分野へ波及していくことでしょう。脱炭素社会実現とともに進展する新しい価値創造や、各種プロジェクトの最新動向の確認も今後のアクションにつながります。今後の業界動向や取り組み事例、最新技術などに関心がある方は、より具体的な情報を積極的に収集し、低炭素建設の可能性について検討してみてください。
参考文献
https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/2024/
https://sumitomocorp.disclosure.site/ja/themes/24
https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/2025/